ISBN:9784863870086、本体価格:1,300円
日本図書コード分類:C0095(一般/単行本/文学/日本文学評論随筆その他)
236頁、寸法:128×189×17mm、重量295g
発刊:2010/12
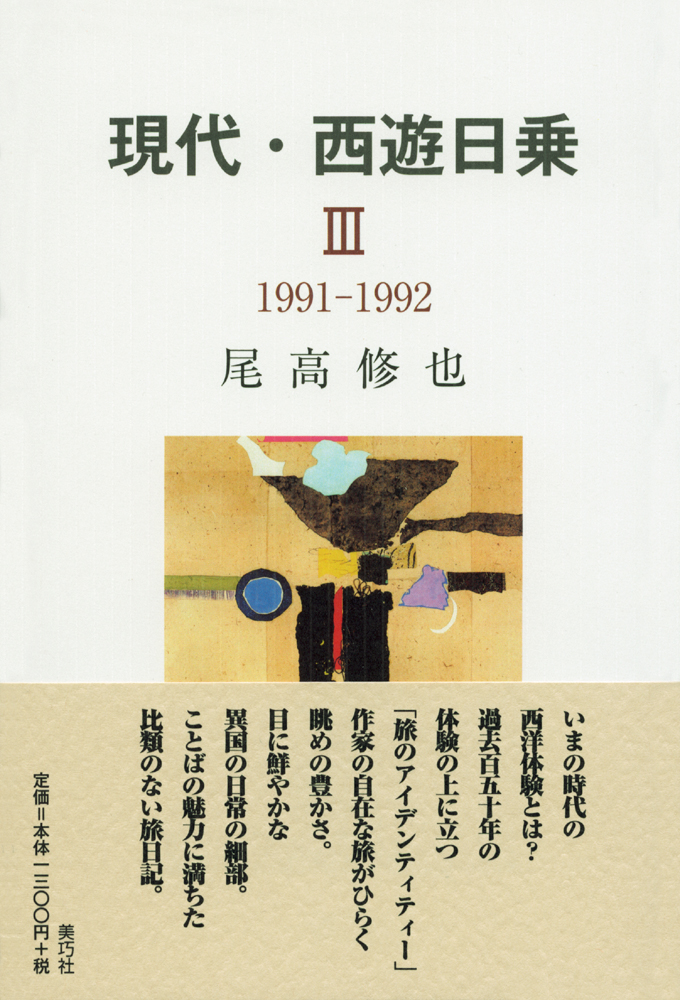
【あとがき】
1991年から1年半ほどの記録を整理して、こんなかたちのものになった。この時期は主に英国に腰を据え、はじめて米国への旅も試みている。米国を知るのが遅れたが、遅まきながら近代日本が最も深くかかわった国の姿を見て、いろいろと考えることがあった。
欧米を見るのに東まわりで行くか西まわりで行くかといえば、明治のはじめから東まわりの旅行者が多かったようだ。新興国日本がまず直面しなければならなかったのはアメリカであり、いわばその絶対的な課題を前にした日本人の、気負いと熱意と好奇心と驚異の念が、いまわれわれが手にする古い記録のなかに生きている。
その後の時代、昭和戦前期と戦後の一時期の旅行者にとっては、アメリカは強大な「ドルの国」であった。彼らの経験は、ドルが世界を支配していることを痛感させられ、日本がいかに貧乏かを認識させられる、というものになった。特に戦後は、アメリカの財団のおかげで旅ができた人も多く、ドルの威光を身に受けたアメリカ体験がいろいろと記録されている。
戦前も戦後も、仕事でアメリカと関係をもった人が少なくなかったのはもちろんである。その記録こそ乏しくても、彼らの経験が日米関係の核心の部分をつくっている。どの分野にせよ、新しい仕事をアメリカ抜きで考えるわけにはいかない時代が長くつづいたからである。
私はといえば、仕事でアメリカとかかわった経験がなく、またアメリカ文学を専門にするということもなかった。私がはじめて「西遊」の旅を思い立ったのは、戦後30年以上もたってからで、すでにドルの威光は弱まりかけ、「ドルの国」アメリカを過度に意識することもなくなっていた。アメリカの大きさや強さが、一漫遊客のうえにものしかかるようだった時代はすでに終わっていた。東まわりで真っ先にアメリカへ行く理由は特になく、私は西への旅を先にしたので、私のアメリカ行きはずいぶん遅れることになってしまった。
遅れたうえにわずか2週間の旅で、実際のところ私はアメリカ体験といえるほどの経験もしていない。したがって、本書の主要部分は、これまでどおりいわゆる「旧世界」の旅の記録である。
英国は1991年に半年滞在する機会があった。私はもともと英文学に親しみ、そちらからヨーロッパ大陸を見てきたようなものなので、実際に英国で暮らしながら何度か大陸へ渡ることにもなった。旅のあいだ、18世紀の「グランド・ツアー」以来の英国人の大陸体験を頭においていた。ヨーロッパの北のはずれのグレート・ブリテン島から大陸へ渡る経験というものに、特殊な興味を感じていたのだといってもいい。
1991年といえば、ゴルバチョフ大統領による「ペレストロイカ」の7年の末にソ連共産党が解体し、ソ連邦が崩壊した年である。バルト三国もウクライナやベラルーシなどの連邦共和国も独立し、先に社会主義を捨てた東欧諸国を含む「東側」の世界が完全に消滅することになった。
私はそんな変動期に英国で暮らし、過去の東欧での見聞を思い出しながら、「東側」の消滅があまりにあっけなくて、簡単には信じられないような思いでいた。が、驚くのはおそらく私が日本人だからで、ヨーロッパの歴史のうえではその種の激変は特に珍らしくもないことだったのかもしれないのだ。
それにしても、私はヨーロッパの政治の歴史を知らず、そのころ考えていたのは、20世紀のロシアとも東欧とも無関係な、昔の日本の東まわりの旅行者たちのことであった。木村毅『日米文学交流史の研究』という本があり、日本とアメリカの文学の「交流」を、文学そのものの関係にとどまらず、文学が広く人間生活に及ぼした影響までを日米両国の過去に探ろうとした大著である。資料を博捜して詳細に語られる、文学を中心とした日米交流史である。大著だがほぼ明治の時代に絞ってある。
昭和35年の出版であるが、その当時たまたま私は大学で木村氏の授業を受けていた。が、氏はこの大著にかかわる話は何もされなかったように憶えている。自身「文化的バタ屋」と称していた氏の仕事の面白さを私が知るようになるのはずっとのちのことである。
同書には、シオドア・ルーズベルト大統領が「忠臣蔵」の翻訳を読んで日本人に興味をもち、日露戦争の講話の斡旋に力をつくしてくれたといったことが出てくるが、木村氏は「日本の文学者で、アメリカを、それで煮しめたほど身につけた者がふたりいる。永井荷風と有島武郎である。」ともいっている。
私はその2人と、岩倉使節団や昭和になってからの正宗白鳥など、アメリカからヨーロッパへ渡った東まわりの旅行者について英国で考えながら、彼らの旅のあとを追ってアメリカへ行きたいとも思っていた。
翌年春、急いで休みをつくって出かけた。ごく短期間だったが、ひと目見たアメリカは興味深かった。が、それは多くの人が仕事で相手にする現代アメリカとは違うものだったはずだ。仕事の日常と重なり合ったアメリカとは別の、そしてすでに見る前に馴染んでしまっているアメリカとも違う、むしろ古い漫遊客のアメリカに近いもので、私はその意味で新鮮な目を保って過去の作家たちの経験につなげようとした。
私はひとりで自由に歩いたが、過去の作家同様、巨大な車社会のアメリカでほとんど車を使わなかったので、当然その見聞はかたよったものになっているであろう。車を使わずに動けるのは大都市だけだから、私はその限りの経験をして、車を使う生活には直接触れることがなかった。
有島武郎はアメリカでもヨーロッパでも都市を憎み、都会の暮らしは「馬鹿げている」と感じていた。前出の木村毅氏は、有島は近代化以前の「農業アメリカに同化して行った」と書いている。いまや古い「農業アメリカ」はどこにもないにせよ、私の旅の記録からアメリカの広大な大地の気配がうかがわれないのは残念なことである。
米国のあと再び英国へ行き、「旧世界」へ戻って、私はまた前年の滞在のつづきのような旅をした。前年知りあった人たちと再会もした。英国の日常世界に親しく包まれるようだったが、それは一面で、旅らしい冒険を何もしなかったということでもあった。たとえばスコットランドへ行っても、遠い見知らぬ土地を本気で探索しなかった。そのための用意も時間もなく、スコットランドの荒涼たる自然の奥へ踏みこんでいくという旅にはならなかった。
アメリカの田舎へ行くことを考えなかったのとそれは似ているであろうか。もしかして、私の行動力が衰えかけているということだろうか。たしかにそう思えなくもない歳になっていると思った。本書は、そんな私の53、4歳の年の旅の記録だが、過去の2巻とはまた多少違った面白さが出ていてくれればと願っている。
2010年10月 尾高 修也
【目次】
平成3年 1991 4月9日-7月15日
ロンドン カールシャルトン・ビーチーズ ソールズベリー ウェイマス トーキー ダートマス トットネス ファルマス ボードミン パドストウ セント・マウズ プリマス ピトロホリー ブレア・アソール カールシャルトン・ビーチーズ ロンドン ウィンザー モンキー・アイランド マーロウ バース エディンバラ ウィンダーミア グラスミア ストラットフォード・アポン・エイヴォン ヨーク リーズ ハワース ロンドン カールシャルトン・ビーチーズ カンタベリー ノッティンガム イーストウッド クロムフォード ベイクウェル バスロウ ハザセージ シェフィールド チェスター シュルーズベリー アイロンブリッジ スノードニア国立公園 トーキー カールシャルトン・ビーチーズ ケンブリッジ パーレイ バーナム ロンドン
平成3年 1991 7月16日-9月21日
ロンドン ブリュッセル ブリュージュ パリ ヴェルサイユ モナコ モンテカルロ マントン サン・レモ サンタ・マルゲリータ ポルトフィーノ フィレンツェ ルッカ ローマ ボローニャ ブレッシア マントヴァ ルッツェルン ツェルマット バーゼル コルマール ガルミッシュ・パルテンキルヘン ボン アムステルダム カールシャルトン・ビーチーズ ロンドン パリ ヴヴェイ ヴェネツィア フィレンツェ ルガーノ バーゼル ハイデルベルク フランクフルト カールシャルトン・ビーチーズ バーナム ロンドン
平成4年 1992 3月18日-3月31日
シアトル タコマ ボストン ワシントン マウント・ヴァーノン アレクサンドリア ニューヨーク シアトル
平成4年 1992 7月27日-8月25日
クアラルンプール ロンドン グラスゴー エア アロウェイ ニュー・ラナーク フォート・ウィリアム オーバン スターリング ハロゲイト チェリトナム テトベリー バイベリー ボートン・オン・ザ・ウォーター ローワー・スローター トーキー タヴィストック バーンステイプル クロイド ルー ロンドン オックスフォード パーレイ クアラウンプール
あとがき
カバー原画・若松光一郎“西風のみたもの”
【著者紹介】
〔著者〕
尾高 修也